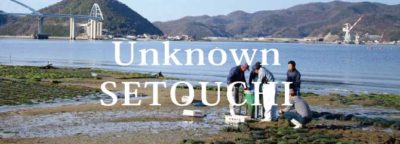西日本で「一番」の薪ストーブ店。
株式会社小畠
1953年に現代表の父親が創業。設計、施工の技術者を含め社員6名。敷地内にある3つのショールームには合計40台の薪ストーブが展示され、そのうち12台は火を入れて試すことができる。
住所:広島県福山市東川口町4丁目1-34
TEL:084-953-0555
営業時間:9:00~18:00(日祝日、第2第4土曜日は10:00~17:00)
定休日:年中無休(年末年始、GW、夏期休暇除く)
http://www.kobatake.co.jp
福山市東川口町の住宅街にある大きな建物。外壁は何百年も時を経たようなレンガと石材で構成され、窓枠にはサビ加工が。大きな扉の向こうには、北欧の薪ストーブや最新のバイオエタノール暖炉が展示されています。薪ストーブや暖炉を販売、施工する小畠が2018年4月にオープンした新しいショールーム「NORDENS FLAMME(ノルデンフランメ)」で、代表の小畠悦男さんに聞いてみました。
― ― すごいショールームですね。
小畠:ノルウェーで見た14世紀末ごろの醸造所をモチーフに、構想から約10年。ようやく完成しました。人と違うことがしたい性格は、昔から変わりません。薪ストーブが好きな人も、凝り性でこだわりが強い人が多いですね。そんなお客様にとって、薪ストーブを「どこで買ったか」はとても重要だと思うんです。だから、ショールームは展示数が多いだけではなく、商品の解説や使い方の知識など、深いコミュニケーションができる場所にしたいと考えていました。その舞台となる建物は、こだわりが強い方々の感性に触れるものにしたいという考えです。「こんなところに、なんでこんな建物が?」と、よくびっくりされます。
― ― なぜ暖炉や薪ストーブを?
小畠:理由は2つあります。ひとつは家業が竈(かまど)と五右衛門風呂から始まった住宅設備会社だったこと。もうひとつは、私の最初の就職先である東京の建材商社が、暖炉の輸入を始めたことでした。幼いころから薪や火には慣れ親しんでいたので、火の焚き方もうまかった。それを見た上司が、立ち上げて間もない暖炉の輸入資材課に僕を配属したんです。後で聞けば、商材としては当時あまりにも異端すぎて誰もやりたがる人がいなかったのが一番の配属理由だったようです。
― ― 暖炉に興味があったわけではないんですね。
小畠:そうですね。ただ、竈屋の息子のDNAかな。火を焚くとしっくりきたのと、人と同じことをしたくない性格なので、市場にあまり出回っていない商材はやりがいがありました。東京でのサラリーマン生活の最後の2年は、暖炉の販売会社で働きました。そこで、暖炉や薪ストーブの施工、煙突の取り付け方などを覚えました。30歳を前に福山に戻って、実家の住宅設備会社で薪ストーブや暖炉の取り扱いを始めたんです。
― ― 当時はどんな反応でしたか?
小畠:薪ストーブは今でこそ全国に約500の販売店がありますが、その頃は全国で7社のみ。福山では薪ストーブを知らない人ばかりで、最初は年間数台しか売れませんでした。その後、全国紙に広告を出したり、地道に販促活動を続けていたら、口コミや紹介で少しずつ足を運んでくれる方が増えました。今では山口や島根など遠方からも来店があり、たくさんの方に選んでいただいています。今年で累計施工台数が2千数百台となりました。西日本では一番の実績です。
― ― 福山はどんな街だと思いますか?
小畠:モノを作る力は、昔から圧倒的に強かったと感じています。独自のノウハウを持った企業がいっぱいあるじゃないですか。その関連企業も地元にたくさんある。我々の業種で言えば、特注の金物が東京だと仕上りに1ヶ月かかる場合でも、地元なら1週間ほどでできてしまう。それが私たちの強みにもなっています。
話を聞き終わるころ、広島ナンバーのクルマに乗った夫婦の来店がありました。ショールームの扉を開けると「すごい」の声。展示された薪ストーブや暖炉をじっくり眺めながら、スタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。

こばたけえつお/株式会社小畠代表取締役。1955年生まれ。東京の大学を卒業後、建材商社に就職。1998年から現職。時間があるときは海釣りに出かけることも。