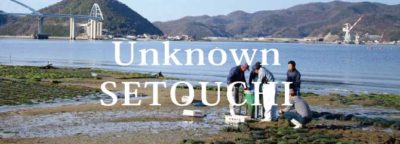能面を外して語る、これからの能の話。
喜多流大島能楽堂
1943年、戦後復興に尽力した3代目・大島久見により建設。1958年より年4回の解説付きの定例鑑賞能を全国に先駆けて開催。中国地方はじめ各地からのファンの期待に応えている。
「小さいころから、能がある生活が当たり前でした。ご飯を食べて、学校に行って、お稽古をする。能が大好きで、能にのめり込んでというわけでもなく、日常として」と笑って話すのは、喜多流大島能楽堂の大島文恵さん。日本の伝統芸能である能の家に生まれ、育った、大島さんに会いに行きました。
ーー能ってなんですか?
大島:そもそもの成り立ちは室町時代。観阿弥(かんあみ)、世阿弥(ぜあみ)という親子の役者が大成したと言われています。普通のお芝居と違って、謡(うたい)や囃子などの音楽を伴ってお話が進んでいくという特徴があって。
もう一つ、いろんな種類の面を付けて演じる特徴を持っています。面を使う芸能は海外にもありますが、そもそも面を付けるというのは、面を付けることによって、人間以上の力を得て特別な存在になるという意味。能はもともと、神々に奉納する意味合いが強くて、神事の延長のような芸能でした。能舞台には神が宿ると言われる松の絵(鏡松)があります。古来よりこの松に降りて来られる神様に対して芸を捧げているという意味からこの松があるのです。
能の演目には、いろんなレパートリーがあって、神話や日本各地に伝わる伝説を題材にしたものだったり、歴史に名を馳せた人物が霊となって現れて、武勇伝や現代に伝わる歴史的なエピソードを物語るという内容もあります。歴史、文学、和歌など、さまざまな日本に伝わる事柄を学ぶことができます。
ーー女性も能ができるんですね
大島:能の舞台は昔から相撲の土俵と同じように神聖な場所とされ、男性が演じるものとされてきたんですね。今でこそ私の姉も含め、女性で活動されたり演じられる方も多くいらっしゃいますが、以前までは女性は認めないというルールもありました。
私は、小さいころから父や祖父から稽古を受けてきて、大学に入ってサークルで能を教えたりもしていましたが、自分がプロでやっていくイメージはなかったですね。ただ、自分が学んで深く携わっているものを伝えていけたらいいなという気持ちはありました。
十数年前から小学校で能の体験授業を行っています。もともと姉の手伝いとして始めましたが、今では大島能楽堂として年間20 校ほど教えに行っています。子供の頃に1度でも習ったことがあれば、それだけで大人になった時に身近に感じてもらえると思うんです。ほかにもカルチャーセンターに教えに行っています。謡をうたったりすることで興味を持って、本物を見てみたいなと言ってくれる人もいます。
日本の伝統芸能を守り伝えていくのは日本人が主体にならないと、と思いますし、もっと裾野を広げて、いろんなことでアンテナに引っ掛かるような活動をしていくのが大切ですね。例えば、子供の能のコンクールみたいなことができたらいいなと思います。能に親しんでくれた子供たちが一堂に会して発表できる場が作れたら。
そういう発表会とプロの公演をドッキングさせて本物にも触れてもらえるようなことができたらいいですね。

おおしまふみえ/喜多流大島能楽堂 教士。1977年福山生まれ。大学時代より、能研究クラブで能を教えるなど、現在は学校での能授業や体験学習に積極的に取り組み、能の普及と啓発に努めている。